蒲生田原発を阻止した先輩たち
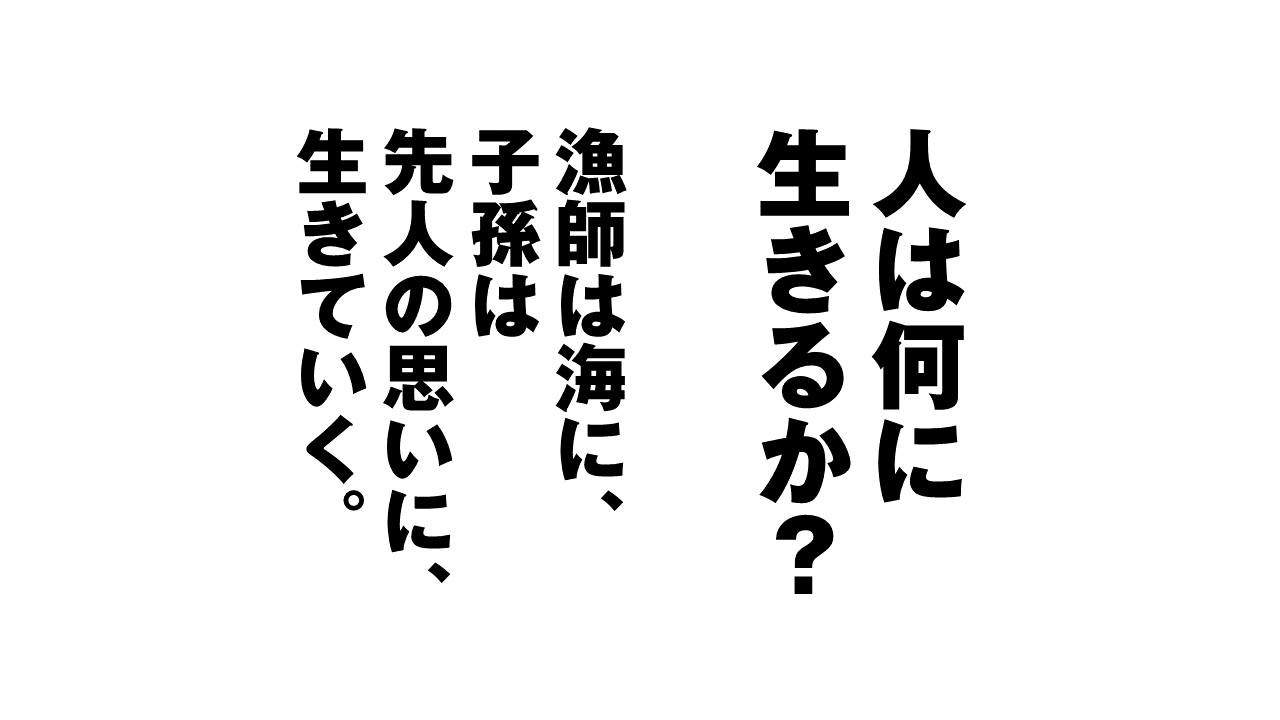
椿泊は阿南のへき地。
人は減り、産業は廃れ。
椿泊小学校は児童数8人。
いまや存亡の危機にあります。
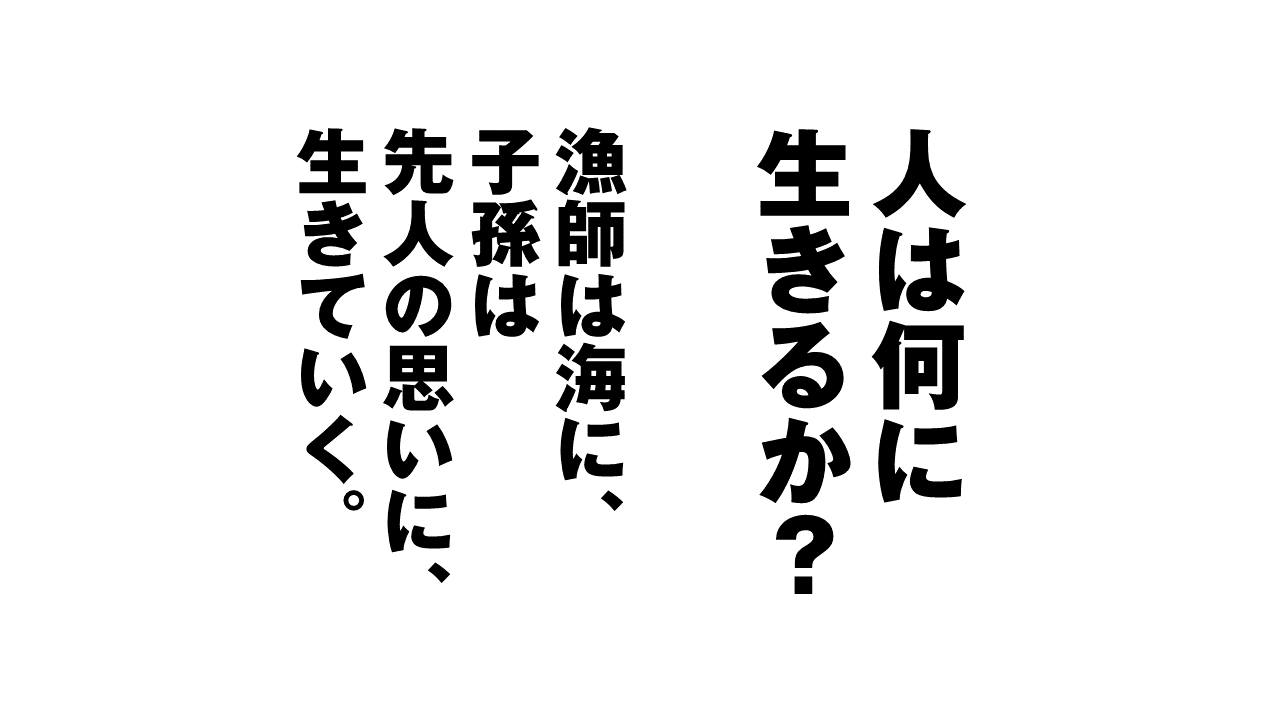
だが、私は椿泊に対し、畏敬の念を持っています。そのことを記しておきたいと思います。
私は、若い頃、コピーライターの駆け出しアルバイトでしたが、大阪電通の仕事で福井県若狭の原発対策の住民リレーションとして、「福井新聞への広告記事」を担当させられ、右も左も要領を得ないのに、若狭地区の住民団体、サークル、同好会、愛好会などを取材して回りました。
この経験から、へき地・若狭が原子力で都会大阪の電力需要を支えていると知りました。この、ピラミッド構造は、福島原発も同じで、あそこは311で爆破されましたが、東京の電力需要を支えていたのです。
ここで、一つ総括したいのは、徳島県の原子力政策です。
四国ではへき地愛媛の西端に原子力発電所が出来ました。四国電力伊方発電所です。活断層の上に施設があり、次の地震災害時の対策が懸念されています。
対して、岩盤の強固さから最有力の候補地だった四国の東端、蒲生田原発は、なんと計画に反して建設が阻止されました。それは、漁連や住民が原発による環境破壊を懸念し、長靴、作業着姿で反対陳情に駆け付けたからだと理解しております。
それには徳島県の原子力政策という軸も絡みます。もし、当時、徳島県および阿南市が原子力誘致政策に前のめりなら、原子力施設が立地していたはずだからです。しかし、そうはなりませんでした。
私は、311の福島原発爆発による放射能拡散を同時代に経験し、原発事故の怖さ、そして、それを前提にして果敢にも原発をはねのけた阿南市・椿・福井・蒲生田の先人に感謝の思いでいっぱいです。
いま、経済的な尺度で言えば、椿・福井・蒲生田の疲弊はひどくて、若い子供も激減し、地域コミュニティも成立しかねる状態です。
しかも、この町には原発でできた高速道路も、原発でできた公民館も、原発でできた高速光通信ケーブルテレビも、原発でできた施設も、まったくありません。
それでも、感謝の思いでいっぱいなんです。
なぜか。
それは、かけがえのない環境を徳島県の全域、紀伊水道全域にもたらせてくれるからです。
この、すばらしい民意、高い環境意識、永遠に色あせない郷土愛よりすごい経済って、あるのでしょうか?
現代電力のピラミッド構造のなかで、毅然として原子力をはねのけた先人・英霊たち。その後継者として、私たちはこの疲弊する状況を生き抜き、思いを継承していきたいと願うものです。
椿泊小学校の校歌をご覧ください。「自由はわれらの進む道。」そう、あなたの先人が、反対の自由を掲げ、かけがえのない環境を守ってくれました。「清く正しく 平和まもらん。」そう、あなたの先人が、かけがえのない平和環境を守ってくれました。
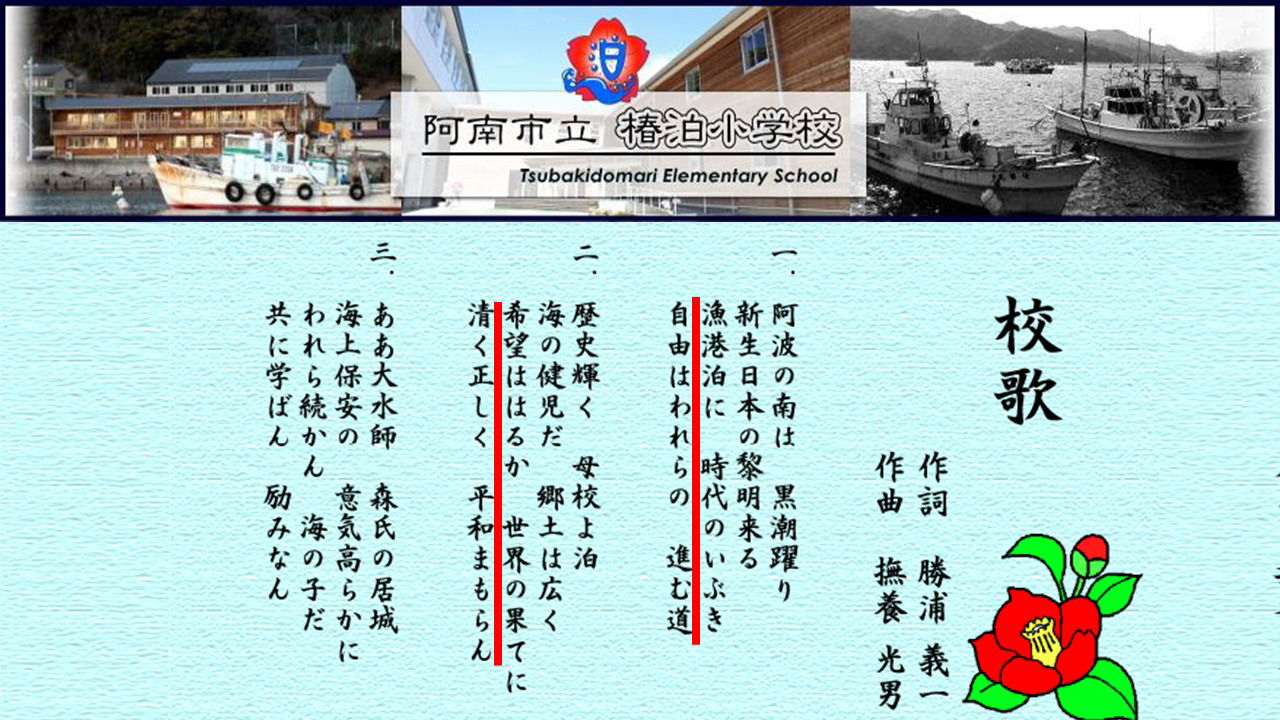
政治とは何か?
首長の決断とは何か?
私は2022年の今、椿泊が廃れゆくその中で、大事なものを見失うことなく守り通した英断、そして住民の総意に畏敬を表します。

※写真:蒲生田岬
極論を言いますが、仮に漁港がさびれ住民がいなくなっても、核物質放散のない環境を死守した事実は永久に不滅です。そして、環境さえ死守できれば、やがて数百年数千年あとでも、また子孫たちはここで海とともに生きることができるからです。
私たちが擁立すべきリーダーには、その揺るぎなき人生観・世界観が問われていると思います。
なぜなら、私たちは数年の任期だけでものごとを判断するのではなく、子々孫々の代にいたるまで責任を負っているからです。
■同地区は二分し今でもしこりは残っている
原発蒲生田発電所という経済繁栄を夢見た半数の住民と。いや生活の海を守るんだという半数の住民と。それが50年後もしこりになっているとしたら、行政判断はとても重く、とても英断のいる作業だったんではないかと、空想します。
50年前なみなみならぬ土俵際の攻防があったことが伺えます。
首長の任期は4年で、とてもじゃないが、4年で責任を完遂できる課題など行政には一つもありません。そうしたなかで、長年にわたり住民合意の形成という業務を担ってきたならば、それがもつ重責がよくわかるはず。むしろ、理事者よりも長年の担当官のほうが見識に優れているとさえいえる。
じっさい、まだ30代40代と年齢が若ければ、蒲生田発電所という十字架さえ知らないでしょうからね。
さて、経済繁栄を申しますと若狭地区は私が通った30年前からはるかに整備が進み、超高速道路、超ハイテク公民館、超ハイテクホールなどものすごいハイレベルな施設が点在し、住民の雇用も電力関連産業などが受け持っている・・・はずなんですが。人口増加で、豊かな地域生活が満喫できている・・・はずなんですが。実施は、原発稼働率低下に伴う補助金の激減、流出人口に歯止めが利かない、豪華施設が無人で遊んでいるだけなのに維持費がかかる、など、猛烈な負の側面が出ています。
同様の現象は、過疎地立地の原発施設すべてに共通します。そして、常時放射視物質はベント(放散)されているし、災害時はメルトダウンの危機と隣り合わせです。
であるならば、われわれ徳島県は、阿南市は、どうすべきだったのか?また、これからはなにをどうすべきなのか?すでに評決は下されており、環境コンシャスという合意のもとに、じっさい具体的にていねいにことを運ぶしかないと思います。
■自然は財産
かけがえのない自然が残っていれば、そこで産業(漁業)が衰退して、人口がゼロになっても貴重な財産として後世に引き継がれていきます。この資源をどう活用していくのか現在の時点では見つからなくても必ず生み出されていきます。
日本が国家として成立してたかだか1500年しか経っていません。人間だけが地球に存在しているのではありません。全ては歴史が証明してくれます。
■科学技術による経済繁栄と 自然とのバランス
ご反論意見もあります。まとめるとこうかと思います。
●反論「科学技術改革を伴う経済発展」が必要
●栗本の論「自然環境と調和した人間生活」もっと普遍化すると「科学と自然、人間生活はどうあるべきか」ということ
さて、ここで俯瞰してみますといま、一般論や世界あるいは国家経済のすう勢は「科学技術改革を伴う経済発展」を大多数が良しとしている状況です。国家は産官学合わせて科学技術改革を推進をしています。そういう背景から言いますと科学推進論は「国家主流派」の意見だと思います。
これに対し「自然環境と調和した人間生活」は牧歌的で、生ぬるい論に見えるかもしれません。ただ、末尾では、原子力開発を筆頭にいくつか科学技術改革への警鐘を鳴らしておきたいとは思います。
■日本が提唱する未来社会のコンセプト『Society 5.0』
今、日本は構造改革徹底推進や第4次産業革命を掲げ、イノベーションを推進しています。そのエリアが国家戦略特区であるスーパーシティです。科学推進論の提唱する科学技術革新が、ここにはあります。
規制緩和による外資企業の積極誘致、外国人の受け入れ促進、デジタル庁などで準備は万端です。
具体的には、サイバー(仮想)空間とフィジカル(現実)空間を高度に融合させたシステムにより未来型社会を実現するらしいのですが、まだよくわかりません。
■2025年大阪・関西万博で6G展開
6Gでは人間の五感を超えるような、テレパシーのようなコミュニケーションを体験できるそうです。6Gでは毎秒100GB以上(5G最大10GB)1Km2あたり1千万個のデバイス接続可能(5Gは100万個)で音や映像、触感、匂い等の感覚が得られる多感通信が実現するそうです。メタバースという技術もこういう仮想現実を可能にします。
■どこまで行くイノベーション
6Gもメタバースも世界を横断する仮想通貨もワクチンもゲノムも、一握りのテクノクラートが絵図を書いて、各国は第4次産業革命を掲げ、経済追求にひた走っています。もうこの勢いを止めることはできませんし、国民もまたマイナンバーデジタルパスポートという管理の流れを拒絶することもできません。
■「科学と自然、人間生活はどうあるべきか」
原子力開発は災害時は物質的なカタストロフをともなうのでさすがに、国民も半数は行き過ぎた原子力開発に懸念を抱きますが、では先述した見えないデジタルイノベーションはどうなのか。ロボット化、AI、センサリング自動化などで、無人都市、無人工場などが稼働する未来。6Gの強烈な電磁波、そしてゲノム加工された食糧配給。それはまるでオーウエルの描いた1984というSFみたいな世界かもしれません。あるいは、仮想現実を自在に駆使する拡張型人間が支配する社会かもしれません。
わたしは、ここまで行った社会はもはや「人間味」を超えた、まさに、デバイスとしての人間しか居ない社会、なんじゃないかと思います。
これが私の科学技術改革への警鐘です。私は海に浮かび、波の音を聞き、魚をあぶって、一献傾ける。そんななかで生きて死んでいければいいですし、残すんだったらデジタル田園都市でなく、手つかずの田舎風景がいいなと思います。
ただし、県南部、阿南市が経済的にも生き残るためにはエネルギーイノベーションや、デジタルイノベーションを使っての環境調和的な発展は必要だと思います。
例えば、ITサテライト企業の誘致や、バイオマス発電による環境調和エネルギーの創出などです。このバランス感覚を持ちながら、行き過ぎた科学技術推進を制御する、という価値観を有しています。
■姿勢
丁寧に、丁寧に、話し合っていく必要がある、深く重い課題であり、また、先送りすることのできないテーマです。文明のあり方、自身の生き方も含めて問い続けていくことが必要です。
その意味で蒲生田原発は終わったのではなく、今もこうして科学と経済と自然の最適なバランスについて、考えさせてくれます。
